30年程前、サハラ砂漠で働いていたことがある。天然ガス処理プラントの工事現場だった。「灼熱の太陽」と「砂あらし」が印象に残っている。まさに「自然との闘い」であった。砂漠には優美なラクダがいる。しかし、至る所で見かけるのが羊であった。アルジェリアではムトン(仏語)という。
砂漠のわずかな緑を求めて何でも食べる。やわらかい草は少なく、スギナのような、硬い草を食べている。工事現場のごみや缶までなめていた。この「ムトン」は山羊と羊のアイノコなのだ。どちらかと言えば「山羊」に近い。
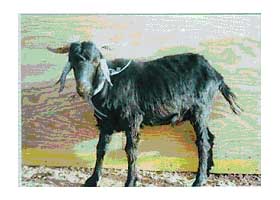
【図1】アルジェリアのひつじ(ムトン)
「ムトン」は、あらゆる料理に使われる肉である。有名な「シシカバブ」や「ショルバ」の料理にはなくてはならないものだ。「独特の油の匂いはあるが、ムトンの丸焼きは豚より絶対においしい」特に「骨付きあばら肉は、味では最高」何回も食べたが、ひきしまっていて、コクがあり、味わい深い。厳しい自然の中を運動している肉だからだろうか?。
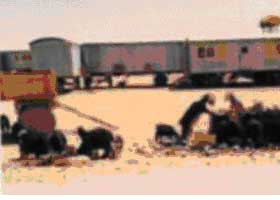
【図2】工事現場でごみを食べる羊(1977年)

【図3】町で羊の肉を売る少女(ガルダイアの町で)
モンゴルの大自然にもひつじが沢山いる。この国には人口(約250万人)の6倍ものひつじがいる。モンゴル遊牧民は古代より牛や馬そして羊などの家畜を飼って生活してきた。
遊牧生活で草原の草を求め、ひつじは自然交配で毎年2割ほど増えていくようだ。食肉用として売られ彼らの収入源となる。
私たちになじみ深いのは、綿羊(メンヨウ)である。毛がふさふさしていて、角は巻貝みたいにカールしている。伸びた毛を刈り取りると「羊毛」になり、「毛糸」になるのである。商売として草原で飼育されている羊は「毛織物」になる綿羊なのだ。
インドの北部カシミール地方で飼育されているのが、有名な「カシミヤ」である。モンゴルでも貴重な産業である。
普通のひつじはヤマ(モンゴル語)と呼ばれている。草原、小高い山の上、市街地などどこにでもいる。これらも、山羊から変化した動物で、結構な山の上まで上ってくる。
主に食肉用として使われる。家庭料理にはなくてはならない。ムトンの蒸し焼き(牛乳の缶の中に焼いた石を入れて蒸す調理法)は野蛮的にうまい。
冬のモンゴルは想像を絶する寒さである。首都ウランバートルでもー40度になる。昨年、仕事で厳冬のモンゴル各地を訪問したが、動物の環境への適応力には驚ろいた。牛や馬そして羊もこの厳しい自然を平然として生きている。人間だったら、簡単に、こごえ死んでしまうだろう。
首都ウランバートルで餌を求めている羊の群れを見た。雪と氷に覆われた大地には何も食べるものがない。公園に来た羊の群れが氷をなめている姿は「生きる原点」を感じた。雪氷の下の草の芽を必死になって探していた。

【図4】雪氷を食べるひつじ(ウランバールにて)

【図5】厳冬のゲルハウスの中で
「自然冷凍ひつじと子供」
これからも、どんな環境にもめげず、世のため、人のために役立つ「羊」として、必死になって生き続けて行きたいと思う。
2002.12.04