「白馬の乳と家族」 =モンゴル鉄道の旅から=
1. 国鉄の保養地へ
「白馬の乳は格別に美味しい!」という事を研究して、観光にしている人がいた。「白馬童子」のことではない。モンゴルの遊牧民のことである。首都ウランバートルから約100キロ北にある国鉄の保養地を訪れた時のことである。
ODA(政府途上国援助)の仕事でモンゴル国を訪れたのは、三年前の秋のことだった。
旧ソビエトの社会主義体制の崩壊以後、この国のインフラ施設(道路や発電設備などのこと)は「ガタガタ」になった。工業物資の補給もほとんどなく、貧乏国となった。日本政府は数百ヶ所ある「ソム」と呼ばれる村落に「エンジン発電機」を無償援助することになったのである。「村落発電施設改修計画」と言う名称のプロジェクトである。
当時、一番ひどい村落は、8年間も「無電灯部落」だった。旧ソビエトが供給してきた発電設備は、老朽化し故障したままだった。修理部品や燃料などの補給も止まった。北西部と南部の7カ村を訪ずれ、エンジン発電機の技術指導を行ってきた。そして、村落の実態と遊牧民の生活がいかに大変なものかも体験した。
ODAは毎年続き、今年で4年目になる。すでに約300台の「エンジン発電機」が供与されている。現在、国民一人あたりに対する援助額では、一番多い国である。
昨年の夏、再々度モンゴルを訪れた。今回、納入分44カ村に対して「発電機管理者の
教育」のためである。
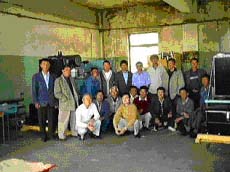 「エンジン発電機の技術指導」 (図 1)
「エンジン発電機の技術指導」 (図 1)
約1ヶ月の教育が終わったので、休養を兼ねて、「モンゴル鉄道の旅」に出かけた。
同行の教育担当者T氏と現地人通訳B氏と私を含め3人の旅である。
ウランバートルを朝9時ごろ出発。列車は旧ソビエト時代のものである。西独製らしく、なかなかよく造られている。冷暖房完備で、石炭ボイラーの湯沸器がついていた。列車の中に売店もある。シベリア鉄道の長距離用気動車だ。私達はコンパートメント(6人用個室)を予約していた。1泊2日の旅行企画はすべて通訳に任せてあった。
車窓の風景は、なだらかな丘陵と草原が続く。牛や馬そして羊などの家畜の群れがあちこちに見られてのどかな風景である。都市の景観とは雲泥の違いである。首都圏の雑踏の生きる私にとっては、この上ない気分転換になった。
停車する集落の駅舎は、日本の「地方単線の田舎駅」のような感じである。駅の際には、馬を待たせておくための「停留棒」がある。人々は、家から駅まで馬に乗ってくるからである。「忠犬ハチ公」のような、犬君も待っているのが面白い。
モンゴルの鉄道は南北にしかなく、南は国境を越えて北京まで伸びている。私たちの列車は、ロシアのバイカル湖の方面に向かっている。
持参のパンとコーヒー(社内販売で持ってきてくれる)で朝食をとりながら、同室の老人(元ジャーナリスト)と談笑しているうちに、約三時間余りで目的地に着いてしまった。ここは数少ない国鉄の保養地である。若者のグループや家族連れなど、数十人の観光客が降りた。この集落は数百人程度の部落である。宿泊施設と自然の遊園地、乗馬、川遊び、釣り、丘陵の山登り、キャンプなどが楽しめるようになっている。
私達は、保養所のレストランで昼食を取ったあと、今晩の宿を捜し歩いた。この日の観光客は多く、保養所での宿泊は困難だった。通訳の知人宅も留守であった。結局、保養所の紹介で、一般の民家(ゲルと呼ばれる円形のテント小屋)に泊まる事になった。予約が取れて一人安心し気分は爽快となった。
2.白馬の乳
「馬に乗ろう!早く馬に乗りたいー!」心は踊っていた。大きな川(川幅十mくらい)の近くに、一軒の「ゲル」があった。ここが乗馬観光の「馬宿」である。周囲には、白馬が
何匹もいるではないか。
 「白馬を育てる」(図 2)
「白馬を育てる」(図 2)
 『次男・長男・三男』(図 3)
『次男・長男・三男』(図 3)
この馬宿の、主人は「白馬のミルクは格別においしい」という事を研究し、「観光」にし
たのである。子供と奥さんが、白馬の乳を搾ってさしだしてくれた。ちょっとだけ口にした。なんとなく母乳のような感じだった。しかし、たくさんは飲まなかった。
数年前、モンゴルを訪れたとき、「馬乳酒」を飲んで大変な目にあった。日本人の腹の菌は、ほとんど「牛乳菌(ビフイズ菌)」だそうである。「馬乳酒を飲むと必ず、下痢をする」といっても過言ではない。それもかなり強烈である。胃の中で牛乳菌と馬乳菌とがけんかをするからである。しかし、一度体験すると、その後は大丈夫らしい。
「絞りたての、白馬のミルクは茶色や黒色の馬とは違う!」と言うのだ。ドイツの獣医学者に調査させたそうである。学術的にも興味がある。日本では馬の乳を飲む人など聞いたことがない。絞りたての新鮮なものでないとだめらしい。この主人は灰色の馬を交配させて、徐々に白馬にしてきたらしい。季節にも関係があるようだ。「白馬の乳」に注目したのは、すばらしい。
この家の長男や次男が、乗馬用の馬を持ってきた。「木曾馬」よりも少し大きい。乗り方の説明を聞き、馬に乗った。
長男と次男が途中までエスコートしてくれる。馬の扱い方を教えてくれた。私達が少し慣れているのを見て 途中から引き返していった。はじめは、川辺や平地を「パカパカ」とゆっくり闊歩した。「ドウ、ドウ」と両足で馬の腹をしめつけると「早く行け?」の合図だ。タズナ裁きも解かってきた。鐙にたち、腰を浮かして、ジョッキーのようにスピードを出す。馬は生き物である。操縦は本当に奥深く難しい。
約2時間、私達3人は心行くまで乗馬を楽しんで、馬宿に戻った。子供たちが迎えてくれた。「無事に帰ってきたよー」と挨拶をする。長男が「お疲れさまー」と身振り手振りの表現。なんと、この家の子供は9人もいるではないか。夫婦とあわせ「11人家族」であった。
 「白馬の乳を飲む家族と共に」(図 4)
「白馬の乳を飲む家族と共に」(図 4)
「お茶でもどうぞ!」と、奥さんがゲルの中に案内する。約8メートルの円形のテントハウスである。床はなし、土のまま、粗末なベッドが3つあるだけ。調理は、まな板とストーブだけである。珍しい観光客に、「ご馳走?」を作りはじめた。奥さんは白い麦わら帽姿。にこやかな表情がなんとも楽しそうだった。小麦粉をこねて団子にし、薄く延ばしてフライパンで揚げた「薄パン」は香ばしくておいしかった。飲み物は、牛乳の
固形物を溶かした物である。モンゴル遊牧民の「お茶?」に相当する。
子供たちとも、このおやつ?を食べながら、ご主人と奥さんと談話をした。
驚くことに、子供9人(2歳から26歳まで)みんなこのゲルで生まれたそうである。川があり水に不便はないが、家具や衣類もほとんどなく、家畜と草原だけだ。こんな環境の中でよくぞ9人も育てあげたものだ。日本の大家族とは比較にならない。
ご主人の話によれば、その昔は普通の遊牧民(主に羊を飼い、草原を転々と移りながら暮す)だったそうである。遊牧生活には、ほとんどお金は要らない。この川辺で、生活するようになったのは、かなり前の頃からだという。遊牧生活よりは、現金収入の道を開拓したのである。「何か新商売を」と模索してきたに違いない。
「白馬の乳は世界一おいしい!」ということを発見した?。馬を交配させて、白馬を増やして、観光客に乳を飲ませることを思いたったのである。この家の家畜は馬であり、観光収入で生計を立てている。
3.家族愛
モンゴルの遊牧民に「貧乏」とか「貧困」という言葉は適切ではない。古代?から変わらぬ生活様式を保ってきたからだ。日が昇れば家畜と共に起き、家畜に草を食べさせて移動し、日が暮れるとゲルにもどってくる。月の明かりと星の輝きで夜を過ごす。中国の「晴耕雨読」の生活とは異なる。近代文明国から見たら、「貧乏」という言葉になるだけである。自給自足の生活ができれば、それほど多くの「人工的楽しみ」がなくても、幸せかもしれない。大自然の中で、子供たちは「白馬の乳」を飲んで、すくすくと育っている。10歳の女の子(一人だけ)は、2歳の赤ん坊の面倒をよく見ている。中間の子供たちは、川辺で釣りをしたりして遊んでいた。長男と次男は、すでに成人となり、「乗馬」の仕事をしている。兄弟みんなが助け合って生きている姿が美しい。
外に出て記念写真を撮った。「何か、お礼に!」と思い、子供たちに相撲を取ってあげた。3年前、北西部の村落を訪れたときにも喜ばれた。そして特技の「前転宙返り」をご披露してあげた。
子供たちから、「歓声!」があがる。そして、次から次へと、私のまねをしだした。「ほら、おじさん僕だってできるよー」と。
 「ゲルハウスの中で」(図 5)
「ゲルハウスの中で」(図 5)
 「2歳の坊や乗に乗る」(図 6)
「2歳の坊や乗に乗る」(図 6)
最後に、2歳の坊やが「ビー、ビー」(僕も、僕もの意味)と叫ぶ。「おじさん!見ていて、僕だってできるんだよー」。地べたに頭をつけて、でんぐり返った。「あっ!危ない!」坊やは首をひねってでんぐり返った。すぐ泣き出した。すぐさま10歳の女の子があやした。「この子はたくましく育つに違いない!」。将来、相撲取りになるかも知れない?
「白馬の乳」を飲んで、幼少の頃から馬に乗ってきた。2歳の坊やも乗せてみせてくれた。この家族の連帯感は本当にすばらしい。馬と共に、厳しい自然の中でたくましく生きるこの家族は、現代社会に失われつつある「家族とは?」の原点を教えてくれた。
モンゴル遊牧民の変わりつつある姿と「馬と人間との関係」、「家族愛」が、心に深く残る思い出の旅となった。
(平成13年11月)
(平成14年1月 南信州新聞 <正月特集号>にて掲載