● 読売新聞投稿記事 (産業の発展促がすODAを考えて)
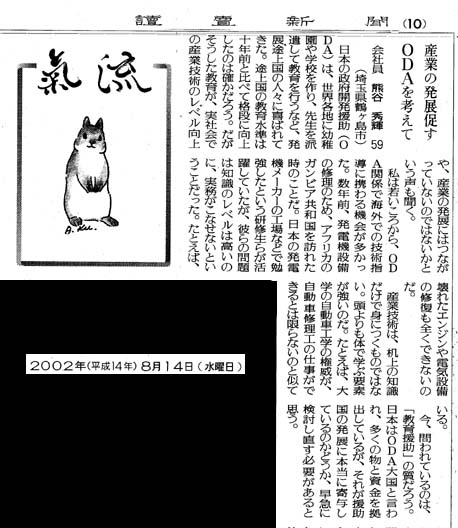
(投稿オリジナル原稿)
ODAの改革について
日本のODAは世界の各地に幼稚園と学校を作り、先生を送り、教育を行い、発展途上国の人々に喜ばれてきた。
一方、「こんなに援助しているのに、その国の産業経済がなぜ発展しないのか?」ということを聞いたことがある。
数年前、発電機関係の仕事でネパールに行った時のことだ。教育学研究所の職員だと言っていた。この「教育学の研究課題?」もODAなのだそうである。
私は若い頃から民間企業で海外の仕事を行ってきた。最近、ODAの教育や技術指導の仕事をする機会に恵まれている。
近頃「ODA教育の質について」政府の諮問委員会が出来たようである。政府関係者や大学教授そして学術研究者が主な委員だと聞く。
「ODAの教育について」一言申し上げたい。その評価について
疑問点が多いからである。
産業技術教育について、従来から行なってきた教育について、反省すべきところは多い。産業技術教育は学校の授業とは違う!紙と鉛筆(近年はコンピュータ)に頼ってきた教育について改善しなければならない。
発展途上国の教育は10年前と比較し、格段に向上してきてい
る。「知識レベル」も先進国のレベルにまで達してきている。
しかし、実社会の産業技術は思ったより向上していないのであ
る。「この不一致をどのような視点で捕らえているか?」が問題
である。「教育レベル向上と産業発展とが大きく食い違っている」
のが実情である。
数年前「ガンビア」を訪問した。発電機設備の修理のODAであった。日本に研修生がきて、各工場を訪問し教育の実習を行い、勉強して帰った。国に帰って各分野で活躍している。コンピュータは扱える。知識レベルも高い。しかし、現実は「やる事がデタラメで何も解っていない」要するに知識だけあって、実務ができないのである。壊れた電気設備は全く修復できないのであった。
「産業技術教育は知識だけでは覚えられない」実務教育と言うのは、頭よりも体で体得する要素のほうが強いからである。」
例えれば、大学の自動車工学の権威が、自動車修理工の仕事が出来ないのと似ている。
今こそ「ODAの教育の質について」問われる時がきた。日本は世界一のODA大国と言われ、物資と金を援助している。
しかし「その国の産業の向上に本当に寄与しているのだろうか?」真剣に検討する必要があろう。
ODAの体質改善について申し上げたい。
従来から外務省、JICAおよびコンサルタント会社の企画、実行そして評価については、問題が多すぎる。
金権に絡みつく一部の官僚とその傘下に連なるJICAの抜本的な、改革をしていただきたい。
プロジェクトの出来栄えを「単に報告書の厚さで」評価するような、「旧態時代の依然とした、官僚的な事なかれ主義」がいまだに横行しているのではないだろうか?
生き残りをかけて、民間企業で働いてきた人でないとこのことは解らない。
「ODAの教育はQC的な評価をすべきである。」発展途上国の人々に本当に感謝されたのか、産業技術教育は本当に身についたのかで評価されなければならない。
「産業の底辺で働く労働者に今や紙と鉛筆はいらない」諮問委員会に、「油と汗で現場で働いてきた実務体験のある教育経験者」を入れていただきたいと願う。
今のODAは、国民が解っていないことが多すぎる。支援と援助の内容は各国によって異なる。政治、経済、文化、産業構造など千差万別で一元的には表現できないだろう。その実態については評価がまちまちである。
「一番、気持ち悪い仕事はODAの仕事である!」と申し上げたい。私たちの税金がこんなに無駄使いされていると思うと「頭にくる」事が多いからである。ODAの予算削減が国会で決まった。物や金をばら撒くよりは「教育の質を改善する」ことがODA予算の削減となることに目覚め、改革を行っていただきたいものである。
発展途上国の人々に明るい希望をもたせて、産業発展に結びつく教育を行いたいものです。政府の改革試案である「援助庁?」には、学識経験者は要らない。政府やJICAの人間に頼らず、民間企業の底辺で実務仕事をしてきた人々を多く採用し「ODAの改革」に目指してもらいたい。 以上
(02/08/09)